「ASEAN」の検索結果 [ 2/2 ]
-
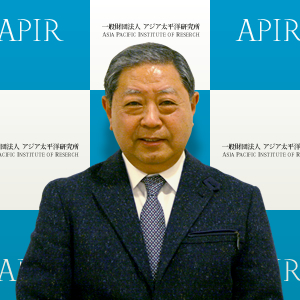
世界の人口と経済に関する超長期データベースの作成
研究プロジェクト
研究プロジェクト » 2013年度 » アジア太平洋地域軸
ABSTRACT
目的
OECDが発表した2060年までの加盟国の実質GDPに関する予測によれば、中国およびインドは、GDPにおいて21世紀中葉にアメリカを凌駕し一人当たりGDPも順調に上昇すると推定されている。英国エコノミスト誌も、2050年までの世界の経済、人口、社会構造等に関する長期予測を発表するなど、世界的に長期予測に関心が高まっている。この研究においては、2100年までの世界160カ国について、人口、実質GDP、および一人当たりGDPを予測し、それをデータベースとして広く一般に提供することを目的とする。
内容
初めに、アンガス・マディソンの歴史統計(西暦1年~2006年)によって、各国の人口と実質GDPの統計的関係性を推定する。次いで、国連の人口推計を手がかりとして、160カ国について、2100年までの実質GDPと一人当たりGDPの年次推定を行う。最後に、それらのデータを公表するための、簡易データベースを構築し、APIRデータとしてホームページ上に英文で公表する。国連の人口推計もIMF経済展望も定期的に改訂されるため、このデータベースも再推定した結果を継続的にアップデートすることとする。
期待される成果と社会還元のイメージ
・人口動態が経済に与える影響を明示する。100年におよぶ超長期予測のベースとなる変数は人口であることにもとづく。
・世界の中には人口増加に伴って一人当たりGDPが低下するという「マルサスのわな」に陥っている国もあることを明らかにする。
・21世紀の中央まで一人当たりGDPの国別格差が縮小する方向に動くが、それ以降再び国別格差が拡大することを示す。
・2100年時点の世界経済においてもアメリカの優位性は保たれ、中国やインドは人口減少でマイナス成長に転移すると予想する。
・ASEAN(+6)、TPP参加予定国、EUなどの地域経済の長期的展望についても明らかにする。
・APIRでの各研究の基礎データとなるとともに、投資先を検討する企業にも、カントリーリスク推定などに利用価値が高いと思われる。
-

環太平洋経済協力をめぐる日・米・中の役割
研究プロジェクト
研究プロジェクト » 2013年度 » アジア太平洋地域軸
ABSTRACT
研究成果概要
本研究では、主要国において政権交代後に一定の傾向を示しつつある通商政策を把握し、TPP(環太平洋連携)協定やRCEP(東アジア地域包括的経済連携)協定の交渉の動向を考察して、アジア太平洋地域における経済協力の枠組みの変化を説明した上で、日本が果たすべき役割を提示しました。詳細はこちら
?目的
この研究の背景には、日・米・中・韓で2012年に政権選挙と、政治的指導者の交代が相次いだことがある。政権交代によって、主要国の環太平洋経済協力を巡る対応はどのように変化するか。地域貿易協定(RTA)に関するTPPのような契約型アプローチと、ASEAN型の合意型アプローチの間で、日本はどのような役割を果たすことができるか。この研究では、地域経済協力の可能性と限界について、国際関係、歴史、政治経済学的視点から分析する。 本研究では、政権交代の通商政策への影響とそれを踏まえた日本の役割への提言を、企業関係者と一般市民を対象にまとめる。
内容
関西を代表する米・中・韓各国政治および国際政治、国際政治経済の専門家で研究会を構成し、それぞれが各国及び国際関係の情勢を調査・分析し、それを会員企業及び一般市民に開かれたオープンなワークショップ・シンポジウムを通じて知見の共有と発展を図る。現地調査にはアメリカで関係学会への出席及び政府関係者へのヒアリングを予定する。 ?政治学的なテーマでのオープンなワークショップ・シンポジウムの開催は、会員企業、市民に対する関西発の特徴ある社会還元となる。
期待される成果と社会還元のイメージ
アジア太平洋地域における地政学的分析を踏まえ、日本がTPP、日中韓間FTA、東アジア地域包括的経済連携(RCEP)交渉にどのような態度で臨むべきか明らかにする。 2012年に日、米、中、韓で改まった政治指導体制が2013年には本格的に始動する。2013年体制がもたらすアジア太平洋地域の新たな政治秩序と、経済協力との関係についての展望を明らかにする。アジア太平洋地域における経済協力と政治的安定性との間の因果関係を分析し、国際政治的リスクの視点から、日本企業が留意すべきポイントを明らかにする。
-

日本経済(月次)予測(2013年3月)<日本企業はChina plus oneに向けて本格的な舵を切ったか?>
経済予測
経済予測 » Monthly Report(日本)
/ DATE :
ABSTRACT
この1ヵ月の予測動向の特徴は、2月後半から両モデルの予測値は3%を超える上昇トレンドを示したが、3月後半には純輸出の予測が反転縮小したことから2%台前半に低下したことだ。今後を占ううえで、純輸出の動向が重要になってくる。 ?2月の貿易統計で注目すべきポイントは、対ASEAN輸出が対中輸出を久方ぶりに上回ったことである。 ?中国がWTOに加盟し国際市場にリンクされるに至り、急速にそのシェアを拡大し2005年半ばにはASEANを抜いた。しかし、その後拡大傾向にあった対中輸出シェアは昨年9月以降、日中関係の悪化により急速に低下したためである。
-
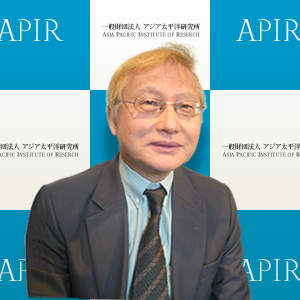
日米アセアン経済の超短期経済予測
研究プロジェクト
研究プロジェクト » 2012年度 » アジア太平洋地域軸
ABSTRACT
リサーチリーダー
熊坂 侑三 ITeconomy CEO研究成果概要
日米の超短期経済モデル(CQM*)が日米経済の現状の景気判断に適し、それが政策当局(特に金融政策者)、エコノミスト、投資家、経営者等の政策決定に役立つことから、日米―ASEAN CQM LINKの構想が生まれました。経済のグローバル化が急速に進展している今、ハイフリークエンシー(High Frequency)統計に基づく現状の景気判断が常に数値とトレンドで客観的になされることは地域経済の景気判断・安定化に役立ちます。最初のステップとして、マレーシア、フィリピン、タイにおけるCQM構築の可能性を調べました。これらの国々においてはCQM構築に十分なハイフリークエンシー統計の整備がなされています。CQMに望ましい季節調整統計によるCQMはタイ経済においてのみ可能でありますが、フィリピン、マレーシアに関しては季節調整がなされていないCQMの構築が可能です。*:「Current Quarter Model」 詳細はこちら研究目的
グローバル経済下、ハイフリークエンシーデーターを活用した超短期経済モデル(CQM)による予測は、現 在の景気動向を常に数値と方向性で捉えることができることから、経済政策当局や企業経営者にとって重要な役割を果たす。ほぼ毎週、日米の景気動向を捉える と同時に、ASEAN諸国の超短期モデル構築にむけた調査を行う。研究内容
○日米経済動向について、重要な経済指標の発表による経済動向の変化を毎月3回の超短期レポートで報告
○詳細な日米経済の動向や連銀等の金融政策のあり方を月次レポートで報告
○年に2?3回セミナーを開催
○ASEAN諸国におけるCQM構築にむけ、タイ、フィリピン、マレーシアに関する調査、CQM構築の具体的構想を作成メンバー
稲田義久 (甲南大学)
<海外協力者(予定)>
国家経済社会開発委員会(タイ)、
国家経済開発庁(フィリピン)、
Bank Negara Malaysia(マレーシア)等 6名程度期待される研究成果
・日米経済動向を数値と方向性で捉えることによる景気判断の明確化
・CQM予測から景気の転換点を市場のコンセンサスよりも約1カ月早く予測
・企業の投資戦略にも重要な情報を提供
・日米とASEAN諸国のCQMをリンクして予測することでアジア地域のリセッションの緩和・回避

