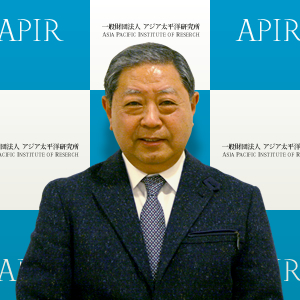「2012年度」の研究・論文一覧 [ 8/9 ]
-

日本企業立地先としての東アジア
研究プロジェクト
研究プロジェクト » 2012年度 » アジア太平洋地域軸
ABSTRACT
リサーチリーダー
鈴木 洋太郎 大阪市立大学教授研究成果概要
本研究は、国際産業立地といった地理的・空間的な側面から、日本企業(関西中小企業)のアジア進出や国際分業進展の課題や展望について考察しています。繊維・アパレル、電機、自動車、外食などの具体的な産業分野ごとに、日本企業のアジア立地戦略について検討しており、また、中国とタイを中心にして、アジアの諸国・諸地域の立地環境上の魅力やリスクについて検討しています。考察を踏まえ、日本企業にとってアジア地域はコスト削減の場所よりも市場開拓の場所になりつつあること、広い意味での日本式サービス(日本的管理方式やメンテナンスなどを含みます)が企業優位性として活用でき、現地での市場開拓の切り口となり得ること等を提言しています。詳細はこちら研究目的
国際産業立地の視点から、日本企業(特に関西中小企業)の東アジアへの展開や国際分業進展について、その課題と展望を明らかにする。研究内容
○企業のアジア立地を専門とする研究者、東アジア地域への立地に興味をもつ企業関係者等によるオープンな研究体制
○日本企業のアジアでの事業活動に関するデータ分析及び現地調査
○日本企業のアジア立地戦略と東アジア地域の立地環境の特徴・動向の考察。企業の事業活動を業種別及び機能別に区分し、時代とともに、どのような業種・機能がどのような立地環境を有するアジアの国・地域に立地する傾向があるのかを分析メンバー
川端基夫 (関西学院大学)
鍬塚賢太郎 (龍谷大学)
藤川昇悟 (阪南大学)
佐藤彰彦 (大阪産業大学)
桜井靖久 (大阪市立大学)期待される研究成果
・東アジア各地域の市場特性、競争条件等の分析
・関西企業の立地戦略の具体例の課題と展望の分析
・直接投資を企図する関西企業、自治体政策への情報提供 -

環太平洋経済協力をめぐる日・米・中の役割
研究プロジェクト
研究プロジェクト » 2012年度 » アジア太平洋地域軸
ABSTRACT
リサーチリーダー
大西 裕 神戸大学教授研究成果概要
本研究は、主要国の政権交代による通商政策への影響を踏まえながら、環太平洋経済協力に対する各国の政策基調を考察し、米中など関係国で高まる政治的不確実性に対する情報を提供し、TPP等で日本の積極的役割が求められていることを示しました。詳細はこちら研究目的
国際政治、国際協力、政治経済学、災害復興協力等の視点から、環太平洋経済協力に対し、日本が果たすべき役割を考察。地域の長期展望を得て、日本及び関西が主導すべき政策的方向性を提言。研究内容
○日本・外国の研究者、産業界、政府関係者の協力のもと研究会・ミニシンポジウムを開催
○中国での現地調査
○多国間交渉における日本の外交的役割として、日本がどのような説得力を発揮できるかを考察
○日米中韓の国内的政治経済状況について、パワーゲームと各々の主張、さらに今年の政権交代が与えるインパクトや選挙結果を分析
○東アジアにおける戦略的災害復興協力体制について提案。 東日本大震災の国際協力の実態も整理・分析メンバー
林 敏彦 (同志社大学)
大矢根聡 (同志社大学)
三宅康之 (関西学院大学)
多湖 淳 (神戸大学)
西山隆行 (甲南大学)
穐原雅人 (ひょうご震災記念21世紀研究機構)期待される研究成果
・米中韓の選挙・政権交代について、選挙の争点及び選挙結果を分析。今後の政治的展望、対外経済政策を見通す。
・過去の貿易自由化交渉を検証し、国際政治経済学の理論に基づいた戦略的視座を得る。
・東日本大震災における防災・復興に関する国際協力の検証により、より有効な支援のあり方を考える。 -
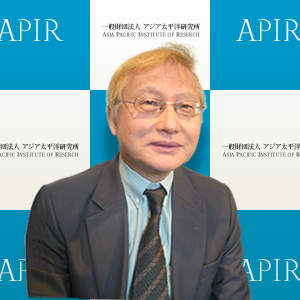
日米アセアン経済の超短期経済予測
研究プロジェクト
研究プロジェクト » 2012年度 » アジア太平洋地域軸
ABSTRACT
リサーチリーダー
熊坂 侑三 ITeconomy CEO研究成果概要
日米の超短期経済モデル(CQM*)が日米経済の現状の景気判断に適し、それが政策当局(特に金融政策者)、エコノミスト、投資家、経営者等の政策決定に役立つことから、日米―ASEAN CQM LINKの構想が生まれました。経済のグローバル化が急速に進展している今、ハイフリークエンシー(High Frequency)統計に基づく現状の景気判断が常に数値とトレンドで客観的になされることは地域経済の景気判断・安定化に役立ちます。最初のステップとして、マレーシア、フィリピン、タイにおけるCQM構築の可能性を調べました。これらの国々においてはCQM構築に十分なハイフリークエンシー統計の整備がなされています。CQMに望ましい季節調整統計によるCQMはタイ経済においてのみ可能でありますが、フィリピン、マレーシアに関しては季節調整がなされていないCQMの構築が可能です。*:「Current Quarter Model」 詳細はこちら研究目的
グローバル経済下、ハイフリークエンシーデーターを活用した超短期経済モデル(CQM)による予測は、現 在の景気動向を常に数値と方向性で捉えることができることから、経済政策当局や企業経営者にとって重要な役割を果たす。ほぼ毎週、日米の景気動向を捉える と同時に、ASEAN諸国の超短期モデル構築にむけた調査を行う。研究内容
○日米経済動向について、重要な経済指標の発表による経済動向の変化を毎月3回の超短期レポートで報告
○詳細な日米経済の動向や連銀等の金融政策のあり方を月次レポートで報告
○年に2?3回セミナーを開催
○ASEAN諸国におけるCQM構築にむけ、タイ、フィリピン、マレーシアに関する調査、CQM構築の具体的構想を作成メンバー
稲田義久 (甲南大学)
<海外協力者(予定)>
国家経済社会開発委員会(タイ)、
国家経済開発庁(フィリピン)、
Bank Negara Malaysia(マレーシア)等 6名程度期待される研究成果
・日米経済動向を数値と方向性で捉えることによる景気判断の明確化
・CQM予測から景気の転換点を市場のコンセンサスよりも約1カ月早く予測
・企業の投資戦略にも重要な情報を提供
・日米とASEAN諸国のCQMをリンクして予測することでアジア地域のリセッションの緩和・回避 -

報告書『税財政改革に向けた研究会(2011年度)』
研究プロジェクト
研究プロジェクト » 2012年度 » その他調査研究
ABSTRACT
税財政改革に向けた研究会(主査:関西大学経済学部教授 橋本恭之氏)の最終報告書を掲載しました。報告書の各章で、消費税、所得税、給与所得控除、寄付金控除、法人税、地球温暖化対策税にスポットを当てて、政権移行後の税財政に関する諸政策を 評価しました。
章別に順次公表中の「ディスカッションペーパー(No23?27,29)」も併せてご覧ください。 -
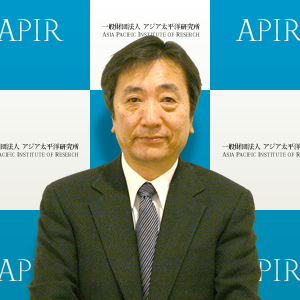
産業活力を強化するための空間構造戦略
研究プロジェクト
研究プロジェクト » 2012年度 » 地域発展戦略
ABSTRACT
リサーチリーダー
林 宜嗣 関西学院大学教授研究成果概要
「東京を成長エンジンに」という発想はわが国産業の高コスト体質を温存するばかりか、地方経済のさらなる衰退を招く。本研究は、生産関数の推計と包絡分析法という2つのアプローチを用いることによって、インプットをアウトプットに変換する「生産の技術的効率性」に地域間格差が見られ、それが経済に大きく影響していること、その背後に「集積の経済」の差が存在することを明らかにした。今後、労働力の大幅な減少が予想される地方においては、「集積の経済」を最大限に高め、産業活力を強化することが不可欠である。そのためにも、国は成長戦略を「地域再生戦略」に転換し、地方分権改革に活かす必要がある。同時に、地方自治体は集積の経済を高めるためにも、現在の行政区域にとらわれない産業立地の空間構造戦略を立てなければならない。詳細はこちら研究目的
地域産業の活性化に極めて重要な要因である「集積の利益」をとりあげ、①産業立地の空間構造と地域経済力の関係を検証し、②生産性を強化するための空間構造を導出した上で、③空間構造戦略の在り方について提言する。研究内容
○わが国の産業立地に関する多角的データ分析
○海外文献研究から日本の地域実態にあった実証モデルの構築
○政策シミュレーションの実施
○各国の空間構造戦略に関する文献研究
○国内外の空間戦略に関する現地調査の実施メンバー
鈴木健司 (日本福祉大学)
林 亮輔 (鹿児島大学)
斎藤成人 (日本政策投資銀行)期待される研究成果
・地域経済の現状と課題、地域産業の活性化に必要な基本条件の明確化
・国・自治体の産業活性化戦略に関する有用な情報提供
・専門ジャーナル、新聞、雑誌等への論文発表、研究所アウトリーチ活動への参加等研究成果
8月3日に第2回研究会を開催しました。
5月11日に第1回研究会を開催しました。 -

日本の金融機関の構造変化とアジア経済
研究プロジェクト
研究プロジェクト » 2012年度 » イノベーション
ABSTRACT
リサーチリーダー
地主 敏樹 神戸大学教授研究成果概要
海外進出が中堅・中小企業にまで浸透し、メガバンクのみならず地方銀行も対応を迫られています。その現状と課題について、今年度は最大進出先である中国を中心に調査・研究を実施しました。その結果、中国進出企業の金融面での主要な障害は対外借入を抑制する「投注差」規制などであり、それら資本規制は人民元取扱の制限と相まって、邦銀にとっても大問題であることが判明しました。進出邦銀は支店網の制約からリテール預金に頼れないので預貸比率規制に左右されますが、利鞘は規制で守られています。ただ、そのような規制は突然に変更されるので、政策方針を察知することが重要です。海外進出への制約が経営上大きな負担となる地銀は中国リスクへ敏感とならざるを得ませんが、メガバンクは規制の緩和もにらんで中国での次のビジネスを模索中です。詳細はこちら研究目的
邦銀の海外再展開や地銀による進出企業への総合的サービスのありかたや効果、進出する邦銀・企業の地元関西における金融構造の変化を分析。研究内容
○中国・東南アジアなど企業進出先の現地調査(邦銀等ヒアリング)
○関西における調査・ヒアリング
○関西の金融機関のデータ収集・分析
○大証・東証及び顧客企業の調査・ヒアリングメンバー
猪口真大 (京都産業大学)
三重野文晴(京都大学)
梶谷 懐 (神戸大学)
岩壷健太郎(神戸大学)
金京拓司 (神戸大学)
砂川伸幸 (神戸大学)
播磨谷浩三(立命館大学)
唐 成 (桃山学院大学)
劉 亜静 (神戸大学大学院生)期待される研究成果
・関経連はじめ経済界への公表、フィードバックの受入れ
・アカデミックな研究論文の作成 -

関西広域経済圏における災害の経済分析
研究プロジェクト
研究プロジェクト » 2012年度 » 地域発展戦略
ABSTRACT
リサーチリーダー
萩原 泰治 神戸大学教授研究成果概要
南海・東南海地震の可能性が指摘される現状で、想定される経済的な被害の把握は国や自治体にとって大変重要です。本研究は、内閣府の「南海トラフの巨大地震モデル検討会」で示されたシミュレーション結果をもとに、近畿地方を中心とする経済的な被害額を推計するものです。同検討会において住宅建物被害において採用された方法を事業所に適用して、被害率と償却対象有形固定資産被害額を推計しました。主に津波を原因とする被害率は、和歌山県、高知県、静岡県など太平洋に面した県で高いという結果になりましたが、被害額に関しては、経済活動の集中している大阪府、愛知県が多く、近畿は被害額の1/3を占めるという結果になりました。研究目的
応用一般均衡モデルを作成し、東南海地震の関西における経済的影響についてシミュレーション分析を行う。研究内容
○基礎的なシミュレーションを行い、長期的影響分析に向けて住宅、投資、人口移動、労働、金融、財政の基礎研究
○短期的な経済被害として、一次被害(建物・工場等の損壊など)により派生する二次被害(生産活動の停滞)に関する分析
○長期的な分析のための阪神淡路大震災以降の神戸市経済に関する分析の整理
○長期的なシミュレーション分析メンバー
玉岡雅之 (神戸大学)
中川聡史 (神戸大学)
宇南山卓 (一橋大学)
中谷 武 (流通科学大学)
橋本紀子 (関西大学)
西山 茂 (神戸学院大学)期待される研究成果
・研究報告書の作成、不定期なWorking Paperのとりまとめと研究発表会の開催
・学界、内外の研究機関での発表研究成果
2月6日に第3回研究会を開催しました。
12月26日に第2回研究会を開催しました。
5月22日に第1回研究会を開催しました。 -

関西企業とアジアの経済統合
研究プロジェクト
研究プロジェクト » 2012年度 » アジア太平洋地域軸
ABSTRACT
リサーチリーダー
阿部 茂行 同志社大学教授研究成果概要
TPPが動き出すことによりアジア大の経済統合が現実味を帯びてきました。もとより「世界の工場」アジアは、デファクトに統合をすすめ、広範囲の生産ネットワークを築いてきたのです。2011年のタイ洪水はそうしたネットワークの中心にあったタイに甚大な被害を与え、世界の自動車・電機電子産業への影響も強いものがありました。このプロジェクトでは、タイ経済の回復過程、そして今後起こりうる変化を分析することにより、今後の経済統合の進展が及ぼす関西企業(ことに中小企業)への影響を考察しました。多国籍企業は人件費等の安さだけで立地決定をしているわけではなく、業種によっては裾野産業が育っていることが重要です。その意味でタイは、関西中小企業に格好の進出機会を与えてくれる、というのが結論です。詳細はこちら研究目的
関西企業の東アジアに進出するモチベーション、技術移転、経済統合への対応、アジアへの貢献等を産業分野別に調査分析し、アジアの枠組みの中で関西経済を見直し、関西経済復権への具体的提言につなげる研究を行う。研究内容
○専門家、企業人を招いた研究会を開催
○関西企業のFTA/EPAに関するヒアリング
○タイにおいて現地企業から聞き取り調査を実施
○経済統合の進展とともに、どのようにサプライチェーンが構築されたか、今後の経済統合がどのようにサプライチェーンを変質させるか等のデータ分析メンバー
Eric D.Ramstetter (国際東アジア研究センター)
上田曜子 (同志社大学)
後藤健太 (関西大学)
久保彰宏 (富山大学)
阿部良太 (神戸大学大学院生)期待される研究成果
・日本・アジアにおける関西企業の立ち位置を統計的に明示
・タイ洪水がもたらした生産ネットワークへの被害実態と対策について客観的に評価
・アジアにおける産業別生産ネットワークの実態の解明により、今後の方向性とリスク回避方法を探究
・日本企業の貢献に関する現地側の評価の明確化
・TPP等経済連携についての関西企業の取組み・期待に関するサーベイ
・関西経済復権につながる具体的な政策研究 -

東南アジアにおける発電・送電事情と将来計画
研究プロジェクト
研究プロジェクト » 2012年度 » イノベーション
ABSTRACT
リサーチリーダー
山本 隆三 富士常葉大学教授研究成果概要
アジア諸国の経済は拡大を続けています。1人当たりの電力需要をみると、例えば、ミャンマーは日本の60分の1ですが、ベトナムは6分の1まで拡大しました。今後、さらに需要は伸びます。需要が拡大することにより、日本企業にはビジネスチャンスが生じます。発送電設備の導入、それに伴う工事、家電製品の販売増が見込めます。温暖化問題に対応するための原子力発電、省エネ設備等の導入でも日本の技術力が期待されています。日本政府も二国間の協定を通しこの動きを後押ししています。一方、将来の安定的な電力供給は、日本企業の進出をも左右する大きな要素でもあります。日本企業のビジネスに多くの影響を与えるベトナムの電力問題を現地調査も交えて分析し、結論として、温暖化対策での二国間協力の推進、発電設備売り込みのポイントなどを提言しました。詳細はこちら研究目的
東南アジア各国の電力需要の伸びを調査し、温暖化問題も考慮したうえでの最適な発電設備の組み合わせを研究。さらに再生可能エネルギー導入の可能性、送電網整備も研究。結果として、日本の関連企業のビジネスチャンス形成につなげる。研究内容
○東南アジア諸国での現地調査
○各国の発電設備建設計画の調査と最適な発電設備の導入の検討、送電線網の建設の検討
○再生可能エネルギー導入の具体化に向けた調査、有力案件の具体的なプロジェクト推進方策の検討メンバー
秋元圭吾 (RITE(地球環境産業技術研究機構))
飯沼芳樹 (海外電力調査会)
上野貴弘 (電力中央研究所)
竹内純子 (国際環境経済研究所)
渡里直広 (海外電力調査会)期待される研究成果
・東南アジア諸国の発電設備の最適化、送電技術の向上、電力供給安定化による国民生活向上・産業・観光振興などへの貢献
・日本企業が持つ発送電関連技術移転への貢献研究成果
1月31日に第4回研究会を開催しました。
10月16日に第3回研究会を開催しました。
7月10日に第2回研究会を開催しました。
4月17日に第1回研究会を開催しました。 -

関西経済予測と関西経済構造分析
研究プロジェクト
研究プロジェクト » 2012年度 » 地域発展戦略
ABSTRACT
リサーチリーダー
高林 喜久生 関西学院大学教授研究成果概要
「国際収支(=輸出-輸入)の地域版」である域際収支(=移出-移入)の分析からは、関西から関東への波及効果は大きく、その逆方向の効果は小さいことがわかりました。また、国・地域の景気指標(CI)の連動関係の分析からは、関西経済はアジア諸国・地域とのつながりが深く、リーマンショック以前は韓国、それ以降は中国からの影響を強く受けていることがわかりました。本研究の結果からも関西の景気変動の独自性は明らかで、速報性・信頼性を持つ関西景気指標(CI)の開発が求められます。分析の結果、関西景気指標は、需要、生産、所得、雇用の4指標をベースに簡便に作成できることがわかりました。また、ユニークな景気指標として、「段ボール生産」が地域の景気の一致指標として要注目です。詳細はこちら研究目的
関西経済の現状分析と予測。関西活性化に資するテーマに関する構造分析の視点からの研究。関西の府県別経済構造分析ならびに関西景気指標の開発と応用。これらを通じて、関西経済の課題と対応策を明らかにする。研究内容
○マクロ計量モデル分析による日本・関西経済の現状分析と予測
○地域産業連関分析による関西経済の構造分析や観光消費の経済波及効果分析、独自の連関表の維持・拡張
○関西景気指標の開発ならびに応用
○アンケート・ヒアリング・現地調査による関西の実態把握
○マクロ経済研究会における会員企業若手スタッフとの共同作業メンバー
稲田義久 (甲南大学)
地主敏樹 (神戸大学)
下田 充 (日本アプライドリサーチ研究所)
入江啓彰 (近畿大学短期大学部)
APIRマクロ経済研究会会員企業メンバー期待される研究成果
・四半期経済予測(2、5、8、11月)の発表
・関西エコノミックインサイト(同上)の発表
・関西経済に焦点を当てた景気討論会の開催研究成果
11月9日に第2回マクロ経済研究会を開催しました。
9月13日に第1回マクロ経済研究会を開催しました。
4月24日に第1回研究会を開催しました。 -

関西地域の投資戦略
研究プロジェクト
研究プロジェクト » 2012年度 » 地域発展戦略
ABSTRACT
リサーチリーダー
小川 一夫 大阪大学教授研究成果概要
本プロジェクトでは、関西企業における高度な技術や専門的な知識を持った外国人財(高度外国人財)の活用状況を調査しました。関西の大学には多くの留学生が学んでいますが、卒業後に関西の企業に就職する割合は高くありません。その原因を明らかにするために、企業と留学生の両方を対象に、共通の質問項目を含むアンケート調査を同時に実施しました。その結果、企業と留学生の間には就業年数にミスマッチがあることがわかりました。一方、企業が期待する能力と留学生が発揮したい能力にはミスマッチは大きくないことから、留学生の定着のためには、多様なニーズを持つ企業と留学生をマッチングさせる仕組みを構築し、外国人にとって快適な生活環境を整備することが必要です。詳細はこちら研究目的
自然災害、円高などの不確実な環境において関西が持続的な発展を維持するには、どのような投資戦略が必要 かを考察する。アジア新興国は高成長を遂げており、その原動力は活発な企業活動にある。このような企業を関西に呼び込むことで、関西における投資の呼び水 となり地域活性化がもたらされることも考えられる。また、留学生が卒業後関西で活躍できる場を提供することにより関西活性化につながることが期待できる。 関西への対内直接投資、人的投資を通して外国人による関西の活性化効果について検討する。研究内容
○研究者、企業関係者、行政関係者、シンクタンク等をメンバーとするオープンな研究体制
○関西への対内直接投資、関西における留学生・外国人労働者に関するデータ収集と分析、留学生・外国人労働者に対する関西活性化に関するアンケート
○アジアにおける対内直接投資が活発な地域、海外からの留学生・労働者を活用し活性化を行っている地域の現地調査メンバー
荒井信幸 (和歌山大学)
松林洋一 (神戸大学)期待される研究成果
・データ分析から関西における対内直接投資、留学生・外国人労働者の現状を描写し、投資や雇用の阻害要因を明確化
・阻害要因を克服し、投資や雇用を促進する戦略の明確化、 戦略の実施による関西経済への効果の定量的情報提供
・海外からの直接投資や人的投資による活性化を達成するために必要な民間の取組み、国・自治体による制度・政策対応の提言